
誰でもできる節約術!貯金を殖やす家計管理のポイントを解説
誰でもできる節約術!貯金を殖やす家計管理のポイントを解説
毎日の生活で無理なく貯金するには、ちょっとした工夫が大切です。誰でも可能な節約のコツとともに、貯金を増やす家計管理のポイントを解説します。まずは、固定費・変動費の違いを理解した上で、食費・光熱費・通信費などの節約方法を知っておきましょう。
目次
家計の負担を減らす節約術とは?

日常的な支出を減らして貯金を増やすには、生活習慣の見直しが必要です。闇雲に節約を始めても長続きしないため、以下のように収入・支出の状況を明確にし、優先的に削れる費目を特定しましょう。
その上で固定費・変動費のバランスを理解し、無駄を減らしながら生活の質を保つことが、無理なく支出を削るためのポイントです。
まずは収入・支出の状況を明確にする
本格的に家計の節約を始める前に、ご家庭の収入・支出の状況を知ることが重要です。収入だけ確認して安心するのではなく、毎月の固定費や変動費、予期せぬ支出まで含めて記録すると、支出の無駄や改善すべきポイントがわかってきます。
まずは、家計簿アプリなどを用いて、日々の支出を記録しましょう。収支の傾向を週単位・月単位で振り返ることで、季節ごとの出費パターンや、生活習慣に潜む無駄が見つかります。
例えば、光熱費や娯楽費などが、夏・冬に急増することがわかれば、事前に対策を講じられるでしょう。
固定費・変動費を把握する
ご家庭の収入・支出の状況を知るとともに、固定費・変動費も把握しておきましょう。
固定費は家賃や通信費、保険料など毎月必ず発生する費用で、節約の効果が大きい部分です。一方、変動費は食費や娯楽費など月ごとに変わる支出であり、工夫次第で調整しやすいのが特徴です。
両者をきちんと把握することで、どこから節約を始めるべきか、優先順位を決めやすくなります。例えば、家賃や保険料などの固定費は、プランの変更や契約の見直しにより、長期的に大きな節約効果を得られる可能性があります。
一方、変動費は日々の小さな工夫の積み重ねが、年間で大きな差になることは珍しくありません。支出をカテゴリーごとに整理して把握することで、どの項目を改善すべきかが一目でわかり、家計全体の節約効果の最大化を図れます。
なお、固定費・変動費の違いや具体例に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。
節約目標を立てる
ただ漠然と「節約しよう」と考えるだけでは長続きしません。毎月いくら貯金したいのか、どの支出を、どの程度削減したいのか具体的に設定すると、日々の消費判断がしやすくなります。
節約目標は現実的で無理のない範囲に設定し、達成度を振り返ることで、節約へのモチベーションを維持することが大切です。また節約目標を立てる際には、短期と長期に分けることで、家計管理がより具体的かつ実行しやすくなります。
例えば、月々の食費を10%削減することを短期目標にして、年間で一定額の貯金を増やすことを長期目標とすれば、毎日の節約を習慣にしやすくなるでしょう。
無駄遣いしないための習慣づくりに関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。こちらも参考にしてみましょう。
節約のための習慣づくりについて、もっと詳しく知りたい方はこちら
食費に関するおすすめの節約術

ここからは、家計の中でもとりわけ大きな支出を占める食費と光熱費、および通信費に関して、節約のコツを具体的に解説します。まずは、多くのご家庭で最も大きな支出になりがちな、食費の節約術から確認していきましょう。
無理のない範囲で自炊を基本とする
食費を節約するには、自炊を基本とすることが重要です。外食やコンビニ弁当などを続けると、どうしても食費が膨らんでしまいます。
できる限り自炊を続けることで、食材の使い回しや量の調整などが可能になり、食費を抑えつつ、栄養バランスも整えやすくなります。
特に毎日仕事で忙しい方は、簡単に作れるレシピを参考にしつつ、時短料理を心がけるのがよいでしょう。例えば、まとめて調理した野菜を小分けして冷凍保存することで、その日に使う分だけ解凍して、無駄なく消費できます。
まとめ買いと冷凍保存で無駄をなくす
特売日やまとめ買いを活用し、食材を適切に冷凍保存すれば、無駄な買い物や廃棄を減らせます。
さまざまな食材の中でも、とりわけ肉・魚や野菜は、冷凍により鮮度を保ちつつ長期保存が可能です。買い物の回数も減らせるため、交通費や時間の節約にもつながるでしょう。
また、冷凍保存を活用することで、余った食材によるレシピを考える習慣を身につけられます。例えば、余った野菜や肉を一緒に炒めて冷凍しておけば、忙しい日の簡単料理としても使えるのでおすすめです。
さらに下味もつけて冷凍しておくと、解凍後すぐに調理でき、外食や惣菜の利用を減らす効果も期待できます。結果的に食費の節約だけでなく、健康的な食生活の維持にも役立つでしょう。
割引や特売日を上手に活用する
スーパーの特売日や割引なども、日々の食費の節約に役立ちます。最寄りのスーパーの特売日や割引情報などを日常的にチェックしておき、安く買い物できるようにしておきましょう。
例えば、週末に特売日を狙ってまとめ買いをすると、必要な量だけ確保でき、無駄な出費の抑制につながります。
さらに、閉店前の時間帯や週ごとの特売日を把握しておくと、必要なものを安く手に入れる機会を増やせます。生活に支障がない範囲で、食材ごとに購入する店舗を分けるのもおすすめです。
ただし、安いからと不要なものまで購入すると、逆効果になってしまうので注意が必要です。毎週使う分だけ、計画的に購入することが大切です。
光熱費に関するおすすめの節約術

次に、光熱費を節約するために、押さえておくべきポイントを解説します。光熱費は毎月確実に発生する固定費の一部でありながら、節約効果が大きいコストです。この機会に、電気やガス・水道の使い方を見直してみましょう。
消費電力の大きい電化製品の使い方を工夫する
冷蔵庫やエアコン・洗濯機など消費電力の大きい電化製品は、使い方次第で毎月の電気代が大きく変わります。
例えば、エアコンは設定温度を夏は1度高く、冬は1度低く設定するだけでも、約10%の電気代節約につながるとされます。洗濯機はまとめ洗いをしたり、冷蔵庫・冷凍庫は食材の入れ方を工夫したりすることで、無駄な電力消費の抑制につながります。
また、電化製品の待機電力も年間で考えると相応のコストになるため、使用していない製品はコンセントを抜くか、節電タップを活用しましょう。こういった日々の工夫により、年間で数千円~数万円の節約になることもあります。
古い電化製品を買い替える
古い電化製品は省エネ性能が低く、同じ使用時間でも電気代が高くなりがちです。特にエアコンや冷蔵庫・洗濯機などは長時間稼働するため、買い替えによる節約効果が大きく現れます。購入から10年以上経過している製品は、積極的に買い替えを検討しましょう。
最新の省エネ家電は初期費用はかかるものの、年間の電気代削減が期待でき、長期的に見れば元が取れるケースがほとんどです。新しい電化製品は操作性や機能面でも進化しており、利便性も向上します。
お風呂やキッチンの使い方を工夫する
お風呂の湯量を適切に調整したり、シャワーの時間を短くしたりすれば、ガス代や水道代を節約できます。
またキッチンでは、鍋の蓋を使って加熱時間を短縮したり、まとめて茹でる工夫なども効果的です。食器洗いなども、お湯の温度を必要最低限に抑えつつ、効率的に使うように心がけましょう。こうした日々の小さな意識が積み重なると、年間で大きな節約になります。
節水アイテムを導入する
節水シャワーヘッドや蛇口の節水器具なども、毎月の水道代を抑えるのに役立つアイテムです。初期投資は必要ですが、自動的に水の使用量を減らせるので、長期的な節約効果が期待できます。
特に家族が多いご家庭では節水の効果が大きく、毎月の支出を着実に減らせるでしょう。節水器具を使うことで湯量や水量をコントロールしやすくなり、生活の中で無駄な水の使用を防ぐ習慣も身につきます。
通信費に関するおすすめの節約術
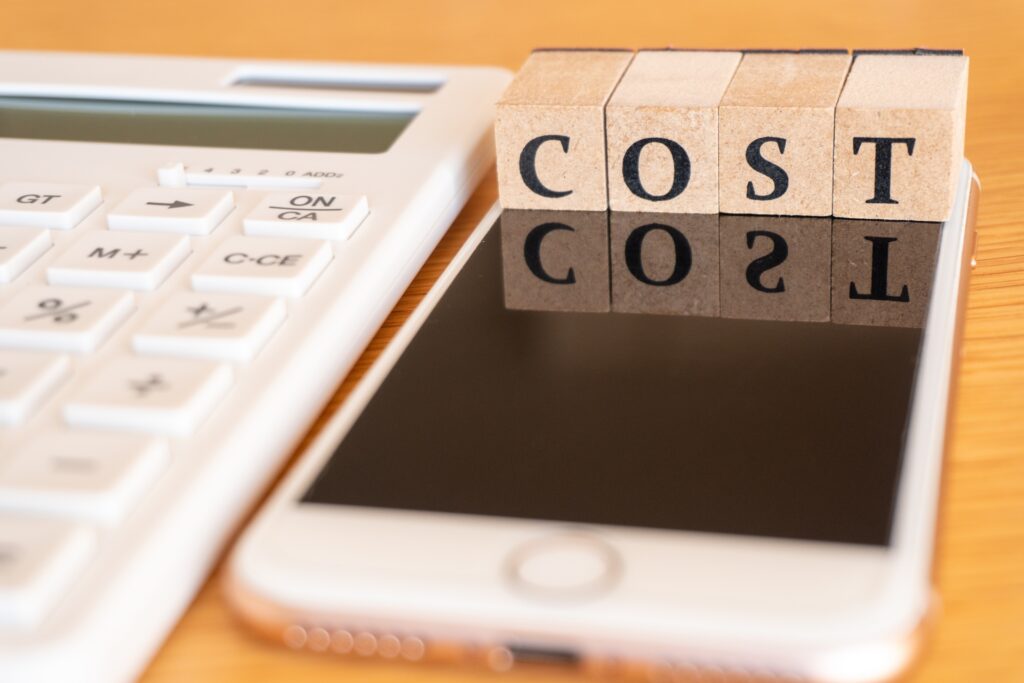
続いて、通信費をうまく節約するコツを紹介します。現代の生活において通信費は欠かせない支出項目ですが、サービス内容を見直すことで、大幅な節約が可能な分野です。
格安SIMやプラン変更でスマホ代を抑える
スマホの通信費は、契約キャリアや料金プランを見直すことで大きく節約できるので、積極的に検討すべき節約のポイントです。
使用データ量に合わせて格安SIMや低容量プランに変更すれば、毎月数千円単位でのコストダウンになるケースは珍しくありません。特に、家族全員のプランをまとめて見直すと効果が大きく、月1万円前後の節約につながることもあります。
また、必要なデータ容量を正確に把握することで、余計なオプション契約を避けることも大切です。定期的に見直しを図ることで通信費の無駄を減らし、家計全体の負担を軽くできます。
不要なサービス・オプションを解約する
ほとんど使っていないにもかかわらず、契約を続けているサービスは、思い切って解約することで無駄な出費を防ぐことが大事です。特に、動画や音楽・アプリなどのサブスクリプションサービスは、気付かないうちに契約が増えがちで、家計の負担になっているケースが多くあります。
不要なサービスはすぐに解約し、毎月の家計の負担を減らしましょう。インターネットやモバイル通信に関するオプションも同様です。これから契約するサービスに関しても、家計簿アプリなどで支出状況を把握し、利用頻度や必要性を定期的に確認しましょう。
無理をせず節約するためのポイント

無理せず節約を続けるには、ストレスをためすぎない工夫が必要です。極端な節約は反動を招きやすく、結果的に浪費につながってしまう場合があります。
持続可能な節約習慣を身につけるために、以下のポイントを意識しましょう。心理的な負担を軽減しつつ、着実に成果を上げることが大切です。
「やめる」より「減らす」でストレスを避ける
節約を意識するあまり、好きなことや楽しみを急にやめるとストレスがたまり、浪費の原因になってしまいがちです。頻度や量を少しずつ減らすことで、精神的な負担を抑えつつ、支出を自然に抑えることを意識しましょう。
例えば、外食を月に数回減らしたり、飲み物を自宅で作ったりなど、無理のない範囲で調整すると継続しやすくなります。「やめる」より「減らす」という考え方は心理的負担が少なく、家族や自分自身の生活リズムを崩さずに、節約を実践するポイントです。
節約の「見える化」で成果を実感する
支出の詳細な記録により、毎月どれだけ節約できたかを可視化するのは、モチベーションの維持に非常に有効です。数字で成果が確認できると家計管理も楽しくなり、次の節約を考えるきっかけにもなるでしょう。
家計簿アプリやスプレッドシートを活用して、食費・光熱費・通信費などの項目別に、節約効果をグラフ化すると成果が一目でわかります。加えて、節約できた金額を貯金専用口座に移せば、貯金の増加を実感できるでしょう。
さらに、定期的な振り返りの時間もつくり、うまくいった点と改善点を整理することで、より効果的な節約方法を見つけられます。
電気料金プランや電力会社の変更も検討しよう

家計管理の基本は、収入と支出の可視化から始まります。その上で食費・光熱費・通信費など、大きな支出項目を無理のない範囲で見直すことが大切です。日々の小さな工夫や習慣の改善でも、長期的には、大きな節約効果が期待できます。
なお、光熱費の中でも電気代は工夫次第で削減しやすい項目です。契約中の料金プランを見直したり、生活スタイルに合った電力会社へ乗り換えたりすることで、毎月の支出を効率的に減らせます。
近年は新電力を中心に、ご家庭でお得に選べる電力プランが多くあるので、この機会に乗り換えも検討してみましょう。
また、電気代の節約を考えているなら、電力会社を変更するのもおすすめです。電気料金が安い電力会社に乗り換えれば、それだけで電気代を抑えられる可能性もあります。
エネワンでんきなら電力使用量に合わせて適切なプランをお選びいただけます。電力会社の乗り換えを検討しているなら、ぜひエネワンでんきをご検討ください。
エネワンでんきで電気代がどのくらい安くなるかシミュレーションしてみる
-

エネワンでんき編集部
-
エネワンでんき編集部は、電気代の見直しや節約の工夫、電力会社の選び方など、暮らしに役立つエネルギー情報をわかりやすく丁寧に発信し、日々の生活に寄り添う情報をお届けします。
 【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル
【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル





