
ガス代と電気代はどっちが安い?ガス代・電気代の目安と節約のコツ
ガス代と電気代はどっちが安い?ガス代・電気代の目安と節約のコツ
ご家庭でのエネルギー使用は、主にガスと電気が中心ですが、ガス代と電気代のどちらが安いのか疑問に思ったことはないでしょうか。ガスの種類や電気代などの目安に加えて、節約のコツも具体的に解説します。光熱費を節約する際の参考にしてください。
目次
ガスの種類と料金相場

ガス代と電気代を比較する際に、まずはガスの種類を知っておく必要があります。ご家庭で使用するガスには、都市ガスとプロパンガス(LPガス)の2種類があるので、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
都市ガスの特徴
都市ガスは、メタンを主成分とする天然ガスや、海外から輸入された液化天然ガスを原料としています。その名の通り、主に都市部で提供されており、供給のネットワークが整っているため、安定した利用が可能です。
また都市ガスは、環境負荷が比較的低いエネルギー源としても注目されています。都市部の集合住宅では、ほとんどが都市ガスに対応しており、暖房器具や給湯設備など、プロパンガスと同様にさまざまな用途で利用できます。
プロパンガス(LPガス)の特徴
プロパンガスは、プロパンやブタンを主成分とするガスで、全国各地に提供されています。個別のガスボンベで提供されるため、災害時に迅速に復旧できるのがメリットです。
また、プロパンガスは熱量が高く、使用するガスの量が少なくても同じエネルギーを得られるのが特徴です。ただし、ガス器具を通しての火力は都市ガスと変わらないため、調理や加熱のスピードに差はありません。
さらに、プロパンガスは都市ガスのように地面を掘削して導管に接続する必要がないため、ガスボンベの設置場所が確保できれば導入しやすいという利点があります。また、環境面では、プロパンガスは都市ガス同様に環境負荷が低いとされています。
ガス料金の目安は?
一般家庭におけるガス料金は、主に使用量と契約内容に基づいて決まります。基本料金と従量料金から構成されており、使用量が多いほど料金が高くなる仕組みです。月々のガス使用量が少ないご家庭では、基本料金が主な負担となることが多く、使用量が増えると従量料金が加算されます。
総務省の家計調査(2023年)によると、単身世帯の毎月のガス代の平均は3,359円であり、2人世帯では4,971円、3人世帯では5,591円です。ただし、4人以上になると、世帯人数とガス代にはほとんど相関が見られません。
ガス代は使用量や生活スタイルによって大きく変動するため、ご家庭に合った料金プランを選ぶことが重要です。
一般家庭の電気代の目安
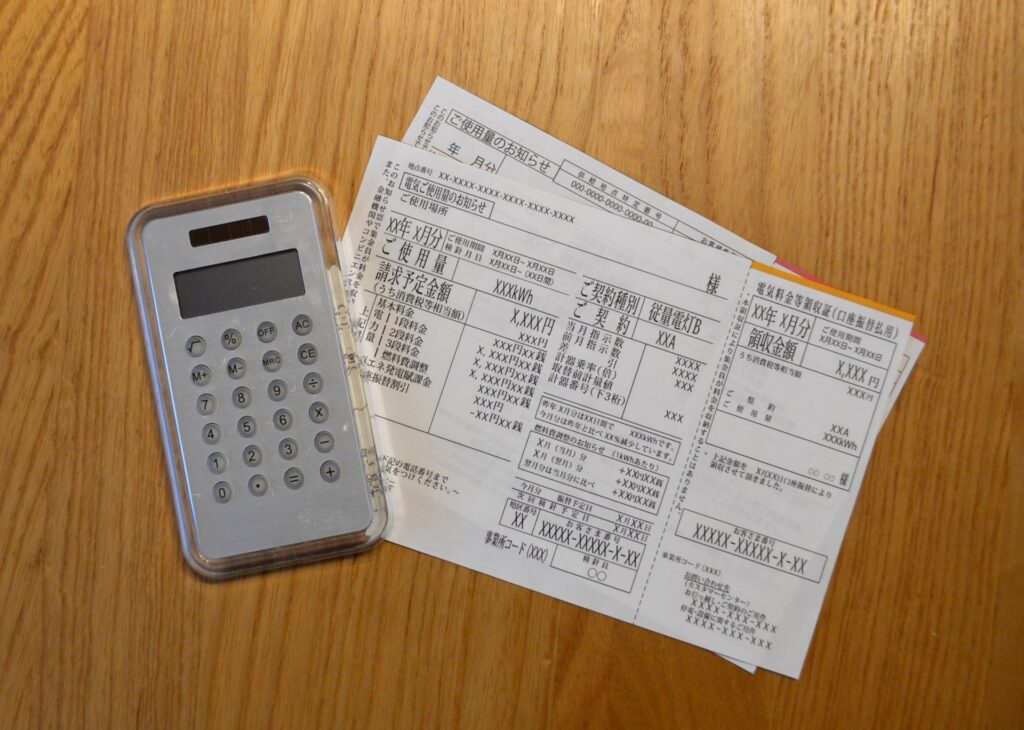
電気代もご家庭の条件や地域・季節によって大きく異なります。一般家庭の平均的な電気代や、世帯人数別・地域別・季節別の電気代の違いも確認しておきましょう。
全体の平均は月に10,000円程度
こちらも総務省の家計調査によると、2023年の一般家庭の電気代(総世帯)は、月額10,222円です。電気代はご家庭のライフスタイルや、生活パターンなどに大きく影響されるため、あくまでも全体の平均ではありますが、毎月10,000円程度が目安と考えておくとよいでしょう。
当然、冷暖房を頻繁に使用するご家庭や、電化製品の多いご家庭では平均よりも高くなる傾向があります。逆に、省エネを意識して生活すれば、毎月の電気代を抑えることも可能です。
世帯人数による電気代の違い
総務省の家計調査を基に、世帯人数ごとの電気代の違いも確認しておきましょう。単身世帯における1カ月の電気代の平均(2023年)は6,726円です。さらに2人世帯では10,940円となり、3人世帯で12,811円、4人世帯では13,532円と増えていく傾向にあります。
上記のように、ガス代は4人以上の世帯になると、世帯人数と料金にはさほど相関が見られません。一方、世帯人数が増えると、家庭の電気使用量も増加するため、電気代も高くなる傾向にあります。
地域別・季節別の電気代の違い
地域別・季節別の電気代の違いも知っておきましょう。まず地域別の電気代の平均は次の通りです 。
| 地域 | 電気代の平均額(2023年) |
| 北海道地方 | 11,254円 |
| 東北地方 | 12,397円 |
| 関東地方 | 9,881円 |
| 北陸地方 | 13,096円 |
| 東海地方 | 10,517円 |
| 近畿地方 | 9,268円 |
| 中国地方 | 11,699円 |
| 四国地方 | 11,225円 |
| 九州地方 | 8,649円 |
| 沖縄地方 | 9,277円 |
また、季節ごとの電気代の平均は、次のように推移しています。
| 調査時期 | 電気代の平均額(2023年) |
| 1~3月期 | 14,646円 |
| 4~6月期 | 9,190円 |
| 7~9月期 | 8,390円 |
| 10~12月期 | 8,514円 |
上記のように、東北地方や北陸地方などの寒冷地では、冬季の暖房費が増加するため、月額の電気代が高くなります。季節ごとの電気代の推移を確認しても、暖房器具が必要な1~3月期の電気代の負担が大きいので、できるだけ光熱費の負担を抑える工夫が必要です。
ガス代と電気代はどっちが安い?

ガス代と電気代のどちらが安いかは、ご家庭の条件や環境に大きく依存します。ここでは、電気・ガスを併用している住宅と、オール電化住宅のコストを比較してみましょう。
電気・ガスの併用とオール電化住宅の比較
一般的にガスと電気とでは、エネルギー単価が高いのは電気ですが、単価の安い深夜電力を使う場合、ガスと同程度の単価になるケースもあります。ガスと電気を併用するご家庭では、用途に応じたエネルギーの使い分けが重要です。
一方、オール電化の住宅では、ガスを使用せず電気のみで生活を賄います。オール電化は契約プラン次第でコストを抑えられますが、一般的に初期設備費用が高くなる傾向にあります。
次に、基本料金を比較してみましょう。東京電力エナジーパートナーの「従量電灯B」を参考にすると、40A契約の基本料金は約1,248円 (2025年1月時点)です。また、一般的なご家庭のプロパンガスの基本料金は、1,650円程度(関東地方の戸建ての場合)です。
オール電化の場合は電気代だけで済むため、基本料金を比較すると、電気とガスを併用するご家庭よりも安くなるケースがほとんどです。
ただし、オール電化の場合は一般的な電気料金プランである「従量電灯」ではなく、オール電化向けの専用プランが適用されることが多く、契約単位もアンペア(A)ではなくキロボルトアンペア(kVA)となります。
契約容量の目安として、従量電灯契約の場合は最高60A(約6kVA)ですが、オール電化ではそれ以上の電力を必要とすることが多く、8kVA(80A相当)やそれ以上の契約になるケースもあります。
※出典:1kWhあたりのエネルギー別単価比較!!|ほかほかアカデミー
※出典:従量電灯B・C|電気料金プラン|東京電力エナジーパートナー株式会社
※出典:プロパンガスの基本料金 | プロパンガス料金消費者協会
電気・ガス併用のメリットとデメリット
電気とガスを併用するご家庭は初期費用が安く、停電時でも生活を維持できるといったメリットがあります。ガスは調理の自由度も高いので、IHよりもガスを好む人も珍しくありません。ご家庭のニーズに合わせて、利用するエネルギーを選択できるのがメリットです。
一方で、上記のように電気とガスの併用は、それぞれの基本料金がかかるため、全体のコストが割高になる場合があります。また、契約管理が複雑になるのも、人によっては避けたいポイントでしょう。
オール電化のメリットとデメリット
オール電化を導入すれば、光熱費(ガスと電気)の契約や支払いを一本化できます。ご家庭内で火を使わないため、安全に生活できるのもメリットです。停電によりライフラインが一時的に絶たれてしまう可能性はあるものの、近年は災害時の普及も早くなっているので、基本的に不便を感じることはないでしょう。
しかしオール電化に伴い、電気温水器やIHクッキングヒーターなどの設備を導入する際には、まとまった資金が必要です。ある程度の期間、資金を溜める必要のあるご家庭も多いでしょう。計画的な導入が求められます。
ガス代・電気代を節約するためのポイント

ガス代・電気代のそれぞれを節約するポイントも押さえておきましょう。日常生活での工夫が、毎月の光熱費の節約につながります。
ガス代を節約するコツ
ガス代を節約するには、給湯温度を適切に設定したり、無駄な湯沸かしを避けたりするのが基本です。湯量を少なくできるように工夫し、設定温度も低くすれば、お湯を沸かすエネルギーを抑えられるので、毎月のガス代の節約につながります。
また、キッチンでもガスコンロだけではなく、電気ケトルや電子レンジなどもうまく活用し、ガスの消費量を抑えるのも効果的です。調理の際には熱効率の良い器具を使い、まとめて作り置きするなどの工夫で、ガスの消費を抑えるよう心掛けましょう。
電気代を節約するコツ
毎月の電気代を抑えるには、電化製品の使用時間を短縮したり、待機電力を削減したりするのが効果的です。特に、エアコンや電気ヒーターなど、消費電力の多い製品の使い方を見直すことで、毎月の電気代を大幅に抑えられるでしょう。
また、LED照明や最新型冷蔵庫など、省エネ性能の高い製品に買い替えることで、使い方を変えなくても電気代の削減が可能です。古い電化製品は積極的に買い替えて、電気を効率的に使えるように工夫しましょう。
消費電力の大きな電化製品の使い方や、節電のポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。
料金プランや電力会社の乗り換えも検討しよう

ガスと電気はそれぞれ特徴や用途が異なり、単純にどちらが安いかを判断するのは難しいのが実態です。エネルギーを選ぶ際は、料金だけでなく、利便性や安全性、災害時の復旧力も考慮する必要があります。
近年、オール電化の住宅も増えているため、ガスと電気の併用とどちらが得になるか検討し、ご家庭に合ったエネルギーの使い方を選択することが大事です。
なお、ガスと電気をセットで契約することで、両者をお得に使えるサービスもあります。セット割引の活用により光熱費全体の負担を軽減できるので、この機会に検討してみましょう。
エネワンでんきは、電気使用量に合わせた最適なプランを選べるほか、さまざまな特典がついたプランも用意しています。電力会社の変更を考えるなら、ぜひエネワンでんきをご検討ください。
エネワンでんきで電気代がいくら安くなるかシミュレーションする
この記事に関連する用語
-

エネワンでんき編集部
-
エネワンでんき編集部は、電気代の見直しや節約の工夫、電力会社の選び方など、暮らしに役立つエネルギー情報をわかりやすく丁寧に発信し、日々の生活に寄り添う情報をお届けします。
 【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル
【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル





