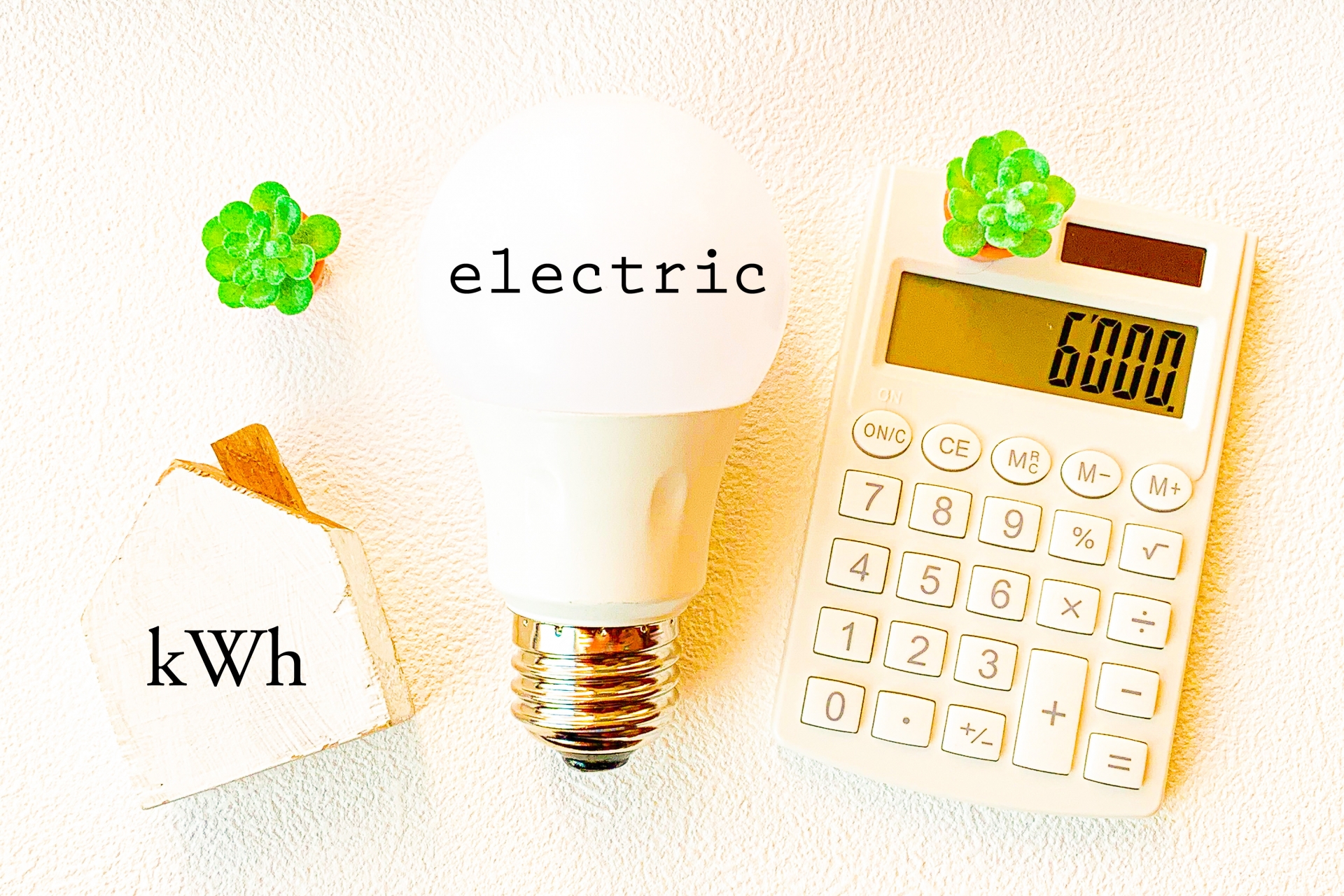電気代3万円はおかしい?電気代が高くなる原因や効果的な節約術
電気代3万円はおかしい?電気代が高くなる原因や効果的な節約術
電気代が月3万円を超えることは、家庭の状況や契約内容によっては十分に起こりえます。内的要因・外的要因を正しく把握し、できる範囲で節約に取り組みましょう。電気代が高くなる理由と月3万円以下に抑える方法について詳しく解説します。
目次
電気代が月3万円を超えるのはおかしい?

電気代が月3万円を超えることは、家庭の状況やライフスタイルによっては珍しいことではありません。ただし、全国的な平均と比べると、やや高めの水準といえる場合もあります。まずは、2024年における世帯人数別・季節別の電気代の平均を確認して、自宅の電気代がどの位置にあるのかを見てみましょう。
一般的に電気代月3万円は高めの水準
総務省統計局の「家計調査 家計収支編」によると、2024年における世帯人数別の電気代の月額平均は次の通りです。
| 世帯人数 | 電気代の月額平均 |
| 1人 | 6,756円 |
| 2人 | 10,878円 |
| 3人 | 12,651円 |
| 4人 | 12,805円 |
| 5人 | 14,413円 |
| 6人以上 | 16,995円 |
また、2024年における季節別の電気代の月額平均は以下のようになっています。
| 時期 | 電気代の月額平均 |
| 1~3月 | 13,265円 |
| 4~6月 | 11,125円 |
| 7~9月 | 11,984円 |
| 10~12月 | 11,657円 |
これらの平均値と比べると、電気代が月3万円というのは、全国的にはやや高めの水準といえるでしょう。もちろん、家族構成や使用状況によって変動はありますが、一般的な目安として参考にしてください。
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)家計調査 家計収支編 総世帯 表番号4 世帯人員・世帯主の年齢階級別
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)家計調査 家計収支編 二人以上の世帯
オール電化なら月3万円を超えることも
電気代月3万円が高すぎるといえるのは、あくまでも電気・ガス併用の一般家庭です。オール電化住宅の場合はガスを使わないため、電気代が月3万円を超えることも珍しくありません。
オール電化住宅では、給湯や暖房に使用する設備により電気代が大きく変動します。冬季に電気代が月10万円を超えるケースも、設備が古く、断熱性能が低い住宅では起こり得ます。
近年は設備の省エネ性能がアップしているものの、省エネ性能に優れたエコキュートなどを導入している場合でも、月3万円を超える可能性があります。
電気代が月3万円を超える内的要因

電気代が月3万円を超えないようにするためには、なぜ電気代が高くなるのかを知ることが重要です。電気代が月3万円を超えてしまう内的要因を知り、ご家庭にあてはまる項目がないか確認しましょう。
生活スタイルが変わっている
電気代が月3万円を超えた場合に考えられる理由の一つに、生活スタイルの変化が挙げられます。ご家庭で最近次のような変化があったのなら、それが電気代にも影響を与えている可能性があります。
- 前より広い家に引越しをした
- 在宅勤務が中心の会社に転職した
- ペットを飼い始めた
- 家族が増えた
- 子どもが夜遅くまで勉強するようになった
上記はいずれも、電力使用量が増えるきっかけになりやすい出来事です。生活スタイルの変化によって電気代が高くなったと考えられる場合は、生活習慣の見直しが必要です。
建物の断熱性能が低い
一般家庭で使用される電化製品の中でも、電気代を大きく左右するのがエアコンです。エアコンの冷暖房の効きが悪い場合は、消費電力がなかなか下がらずに電気代が高くなってしまいます。
冷暖房の効果に大きな影響を与える要素の一つが、建物の断熱性能です。建物に隙間があったり、窓を通して熱が移動しやすい状況だったりする場合、冷暖房の効きが悪くなってしまいます。
エアコンを使っても室内がなかなか快適にならないと感じるなら、建物の断熱性能をチェックしましょう。断熱性能が低い場合は、室内と屋外との熱移動を抑える対策が必須です。
電気を無駄遣いしている
節電をほとんど意識せずに生活している場合は、さまざまな電化製品で電気の無駄遣いが発生しやすくなります。主な電化製品の無駄遣いの例を確認しましょう。
- エアコンの設定温度が高すぎる・低すぎる
- 人がいない部屋の照明をつけっぱなしにしている
- 冷蔵庫の中に食品を詰め込みすぎて冷却効率が下がっている
- テレビを見ていないときも電源をONにしている
- 洗濯乾燥機の使用時間が長すぎる
自分では電化製品を普通に使っているつもりでも、節電の余地は十分にあるものです。節電を意識したことがない方は、電化製品の節約方法を知り、普段の使い方を見直す必要があるでしょう。
消費電力の大きい電化製品を多用している
資源エネルギー庁の資料によると、夏と冬の電化製品の使用割合ランキングは次の通りです。
<夏>
| 1位 | エアコン(38.3%) |
| 2位 | 照明(14.9%) |
| 3位 | 冷蔵庫(12.0%) |
| 4位 | テレビ・DVD(8.2%) |
| 5位 | 炊事(7.8%) |
| 6位 | 待機電力(4.0%) |
| 7位 | 給湯(3.1%) |
| 8位 | 洗濯・乾燥機(1.8%) |
| 9位 | パソコン・ルーター(0.7%) |
| 10位 | 温水便座(0.3%) |
<冬>
| 1位 | エアコン(17.0%) |
| 2位 | 冷蔵庫(14.9%) |
| 3位 | 給湯(12.6%) |
| 4位 | 照明(9.2%) |
| 5位 | 炊事(7.8%) |
| 6位 | 待機電力(5.5%) |
| 7位 | テレビ・DVD(4.2%) |
| 8位 | 電気ストーブ(3.8%) |
| 9位 | 洗濯・乾燥機(2.2%) |
| 10位 | こたつ(2.1%) |
エアコン・冷蔵庫・照明は、季節を問わず電気使用量の上位を占める主要な家電です。これらの電化製品を節電できれば、節約効果をより高めることが可能です。
※出典:夏季の省エネ・節電メニュー | 経済産業省 資源エネルギー庁
※出典:冬季の省エネ・節電メニュー | 経済産業省 資源エネルギー庁
古い電化製品を長期間使っている
電化製品の省エネ性能は年々アップしており、一般的には最新モデルより古いモデルのほうが電気代がかかります。古い電化製品を長期間使っている場合、最新モデルに買い替えることで電気代の節約を図ることが可能です。
内閣府の消費動向調査によると、主な電化製品の平均使用年数は次の通りです。
| 主な電化製品 | 平均使用年数 |
| エアコン | 14.1年 |
| 冷蔵庫 | 14.0年 |
| 洗濯機 | 10.9年 |
| テレビ | 10.7年 |
| パソコン | 7.6年 |
| 掃除機 | 7.5年 |
いずれの電化製品も、買い替え理由で最も多いのは故障です。上記の平均使用年数を買い替え時期の目安にするとよいでしょう。
※出典:消費動向調査 令和6年3月実施調査結果 | 内閣府経済社会総合研究所 景気統計部
電気代が月3万円を超える外的要因

電気代は内的要因だけでなく、外的要因によっても変動します。電気代が月3万円を超える外的要因を知り、電気代の仕組みや電力供給の現状を理解しましょう。
燃料費調整額が高くなっている
燃料費調整額とは、発電にかかる燃料費を電気料金に反映したものです。「燃料費調整単価×電力使用量」の計算式で求められます。
火力発電が主流の日本では、燃料のほとんどを輸入に頼っているのが実情です。燃料の輸入価格は世界情勢や為替レートの影響を受けるため、燃料費調整額を固定すると輸入価格が上がった場合に電力会社が損失を被ることになります。
そのため、燃料費調整額は輸入価格に応じて変動するようになっています。燃料費における一定期間の平均を基準価格と比較し、平均より高い場合は燃料費調整単価を高くし、平均より低ければ単価を下げる仕組みです。
再エネ賦課金が上昇傾向にある
再エネ賦課金とは、再エネで発電された電気を電力会社が買い取るための費用の一部を、消費者が負担するために電気料金に組み込まれているものです。「再エネ賦課金単価×電力使用量」で計算されます。
地球温暖化の抑制は世界規模の課題となっており、再エネ発電を促進するために再エネ賦課金が課されています。再エネ賦課金単価は年度ごとに国が決めており、これまで上昇傾向にあるのが実情です。
なお、再エネ発電の設備が多くなると電力会社の買取量も増えるため、再エネ賦課金単価が上昇傾向にあることは再エネの普及が進んでいる証拠だといえます。
※出典:再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2024年度以降の買取価格等と2024年度の賦課金単価を設定します (METI/経済産業省)
電力の供給が不足している
電気料金が高騰する要因の一つに、国内の電力供給不安や供給余力の減少が挙げられます。東日本大震災以降、原子力発電が相次いで停止し、全体の供給量全体に大きな影響を及ぼしているのです。
また、火力発電所の老朽化や休廃止も進んでおり、国内の電力供給量の大部分を占める火力発電が縮小傾向にあります。これらの要因により電気の需要に対する供給が追いつかなくなると、電気料金の上昇を招いてしまうのです。
漏電で電気代が月3万円を超える可能性は?

電気代の請求が3万円を超えている場合、「どこかで漏電が発生しているのではないか」と疑う方もいるでしょう。電気代と漏電の関係について解説します。
通常は漏電で電気代が高くなることはない
漏電とは、電気が本来流れるべきでない場所へ漏れ出てしまう現象です。電気の通り道を保護する絶縁体が劣化したり傷ついたりすると、漏電が発生することがあります。
漏電は電気を無駄に消費するため、電気料金が高くなる原因にもなります。ただし、漏電が発生すると自動的にブレーカーが切れるようになっているため、通常は漏電で電気代が高くなることはありません。
ブレーカーの故障で電気代が上がるケースも
漏電発生時には漏電ブレーカーが作動し、通電が止まる仕組みになっています。しかし、漏電ブレーカーが故障していると、漏電が止まっていない可能性があります。
漏電を放置したまま電気を使い続けると電気代が上がるほか、感電や火災が起きる原因となってしまうこともあるため、電力会社への連絡など早急な対応が必要です。
漏電が疑われる場合は、ブレーカーのテストを実施してみましょう。すべてのブレーカーを落とした状態で一つずつブレーカーを入れ、急にメーターが急に動く場合は、その回路に問題があるかもしれません。
電気代が月3万円を超えないための節約方法

電気代はさまざまな方法で節約することが可能です。電気代が月3万円を超えないための節約術をご紹介します。
電気の使用量を減らす
電気代の上昇を抑えるには、まず電気の使用量を減らすことが基本です。当たり前のことではありますが、電気代を考えるうえで重要なポイントです。
以下に挙げる電気料金の計算式を見ると、電気の使用量を減らすことがいかに大切かがわかります。
基本料金+電力量料金(電力量料金単価×1カ月の電力使用量)+燃料費調整額(燃料費調整単価×1カ月の電力使用量)+再エネ賦課金(再エネ賦課金単価×1カ月の電力使用量)
基本料金以外の部分は電力使用量に応じて増減するため、電気の使用量を減らせばこれらの外的要因による影響を軽減できます。
電化製品の使い方を見直す
電化製品の電気代は、基本的に「消費電力(kW)×使用時間(h)×電気料金単価(円/kWh)」の計算式で求められます。電気料金単価は電力会社により変動する部分ですが、消費電力と使用時間は電化製品の使い方の見直しで減らすことが可能です。
電気代の節約を図るなら、すべての電化製品において消費電力を抑えることと使用時間を短くすることを意識しましょう。エアコン・冷蔵庫・照明など、電気の使用割合が大きい電化製品の使い方を見直せば、節電効果をより高められます。
電化製品の使い方の見直しについてもっと詳しく知りたい方はこちら
建物の断熱性能を高める
エアコンの冷暖房効率を高めて電気代の節約につなげるためには、建物の断熱性能を高めることが重要です。手軽にできる断熱対策を確認しましょう。
- 厚手のカーテンや丈の長いカーテンを活用する
- 窓に断熱シートや緩衝材を貼る
- 隙間テープなどで窓の隙間をふさぐ
夏の暑い時期には窓から直射日光が入り、室温が上がりやすくなるため、遮熱カーテンやすだれなどを用いて遮熱対策も講じましょう。
省エネ性能が高い電化製品へ買い替える
省エネ法に基づいてスタートしたトップランナー制度により、各メーカーは特定の電化製品における省エネ性能の向上を義務づけられています。10年以上使い続けている電化製品があるなら、最新モデルへの買い替えを検討するのもおすすめです。
一定の省エネ基準を満たした電化製品には緑色のマーク、基準未達成の製品にはオレンジ色のマークが付いています。電化製品の買い替え時には、マークの色も確認しましょう。
資源エネルギー庁の省エネポータルサイトを見ると、10年前に購入したエアコンを最新モデルに買い替えた場合、約15%の省エネにつながるとしています。
※出典:機器の買換で省エネ節約 | 家庭向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト
電気料金プランや電力会社を切り替える
電気代を安くしたい場合は、電気料金プランや電力会社を変更するのもおすすめです。使用状況に合った電力会社に乗り換えることで、電気代を削減できる可能性があります。
エネワンでんきでは、電気使用量に合わせて適切なプランが選べるほか、さまざまな特典のついたプランも用意しています。電力会社の乗り換えを検討しているなら、ぜひエネワンでんきをご検討ください。
エネワンでんきで電気代がどのくらい安くなるかシミュレーションしてみる
電気代を月3万円以下に抑えよう

電気代の月3万円超えは、電化製品の使い方やご家庭の環境、電気の契約内容によっては十分に起こり得ます。内的・外的要因を正しく理解し、無駄の見直しや電力会社の切り替え、省エネ家電の導入などを実践すれば、電気代の削減は可能です。
電気代の節約方法を知ったうえで、できることから少しずつ取り組み、無理のない範囲で電気代を月3万円以下に抑えることを目指しましょう。
-

エネワンでんき編集部
-
エネワンでんき編集部は、電気代の見直しや節約の工夫、電力会社の選び方など、暮らしに役立つエネルギー情報をわかりやすく丁寧に発信し、日々の生活に寄り添う情報をお届けします。
 【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル
【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル