
排気ガスがもたらす環境への影響は?主な成分や削減のポイントも解説
排気ガスがもたらす環境への影響は?主な成分や削減のポイントも解説
自動車や工場から排出される排気ガスは、人間の経済活動の副産物で、地球環境や人体に深刻な影響を及ぼす原因となっています。排気ガスが引き起こす地球温暖化や健康上のリスク、ご家庭でできる削減の取り組みまで、基本的なところを押さえておきましょう。
目次
排気ガスとは何か?

排気ガスは人間の生活に身近なものですが、その正体や発生のメカニズムについて、詳しく理解している人は多くありません。まずは、排気ガスの基本的な性質や、主な成分を知っておきましょう。
排気ガスの定義と発生源
排気ガスとは、化石燃料を燃焼させた際に発生するガスのことで、主にガソリン車やディーゼル車のエンジン・発電所・工場などから、排出される副産物です。これらの施設では燃料が使われる過程で、さまざまな化学物質が発生し、大気中に放出されます。
こうした排出物は大気を汚染する原因となり、地球環境や人体に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、風に乗って広がることで、都市部だけでなく周辺地域にも被害が及ぶケースも珍しくありません。
さらに近年では、ご家庭用の暖房器具や調理器具からも、一定量の排気ガスが発生しています。排気ガスの問題は、産業や交通だけに限られるものではなく、私たちの日常生活全体に深く関わっています。
排気ガスの主な成分
排気ガスには多様な化学物質が含まれており、その組成は燃料の種類や燃焼条件によって異なります。主要な成分は次の通りです。
- 一酸化炭素(CO)
- 二酸化炭素(CO₂)
- 窒素酸化物(NOx)
- 硫黄酸化物(SOx)
- 揮発性有機化合物(VOC)
- 微小粒子状物質(PM2.5)
これらはそれぞれ異なる性質と影響を持ち、環境への負荷や人体への悪影響を引き起こす要因です。特に自動車の排ガスに多く含まれるNOxやPM2.5は、呼吸器系への影響が大きく、近年とりわけ問題視されています。
排気ガスがもたらす環境・人体への影響は?

排気ガスは、以下のように地球規模の環境問題から身近な健康問題に至るまで、多岐にわたる深刻な影響をもたらしています。これらの影響を正しく理解することで、排気ガス削減の必要性がより深く理解できるようになるでしょう。
地球温暖化と排気ガスの関係
排気ガスの中でも、特に二酸化炭素(CO₂)は温室効果ガスの代表格であり、地球温暖化の主因とされています。現代は産業活動や交通機関の発達に伴い、大量のCO₂が大気中に放出されるようになりました。
二酸化炭素は大気中に放出されると、地球から宇宙への熱の放出を妨げ、地球全体の気温上昇を引き起こします。結果として地球の温暖化が進み、異常気象の頻発や海面上昇を引き起こし、農作物の収量低下などにもつながる可能性があります。
気温の上昇によって生態系のバランスが崩れるおそれもあり、環境問題として早急な対策が求められている分野です。
大気汚染による健康リスク
都市部を中心に、深刻化する大気汚染の要因の一つが排気ガスです。上記のように、PM2.5と呼ばれる微粒子は肺の奥まで入り込みやすく、喘息や気管支炎などのリスクを高めるため、とりわけ問題視されています。
特に、子どもや高齢者などの呼吸器が弱い人にとっては、排気ガスの影響が日常生活に影響する可能性もあるので、注意しなければいけません。さらに、長期間吸い続けると循環器系への負担が増すことも指摘されており、心臓病や脳卒中のリスクとも関連する可能性が示唆されています。
生態系や農作物への悪影響
排気ガスに含まれる窒素酸化物や硫黄酸化物は、雨に溶け込むことで酸性雨の原因となるおそれがあります。森林の枯死や湖沼の水質悪化が進行し、生態系全体に悪影響を及ぼす点は、世界中で注目されている問題です。
また、農作物の生育にも影響が出る場合があり、食料供給にも波及するリスクをはらんでいます。特にオゾンなどの光化学スモッグ成分は、光合成の効率を低下させ、収穫量の減少や品質の劣化を引き起こすケースもあります。
国内の排気ガスの排出量の実態と対策

日本は、高度経済成長期に深刻な大気汚染を経験し、克服してきた歴史があります。しかし、ここ10~20年程度は、地球温暖化という新たな課題に直面し、今なお排気ガスの削減は重要な政策課題です。
日本の排気ガス排出量の現状を概観するとともに、国がどのような目標を掲げ、どのような法律や政策で対策を進めているのか、確認しておきましょう。
日本における排気ガス排出量の現状
日本国内では、年間約1億8,000万〜1億9,000万トン程度の二酸化炭素が排出されており、エネルギー部門と運輸部門からの排出が、大きな割合を占めています。特に火力発電による二酸化炭素の排出が多く、全体の温室効果ガス排出の大部分が、エネルギー転換部門(石油や石炭などの一次エネルギーを電力や熱に変える事業活動)に起因するとされています。
また、自動車の普及率が高いことから、都市部を中心に大気汚染物質の濃度上昇も問題視されている状況です。トラックや営業車などの業務用車両も長距離走行が多いため、全体の排出量に大きな影響を与えています。
排気ガス削減に向けた国の取り組み
政府は、地球温暖化対策推進法やエネルギー基本計画を通じて、脱炭素化や排気ガス削減の取り組みを進めるとともに、さまざまな環境規制を導入しています。
例えば、再生可能エネルギーの導入拡大や、燃費性能に優れた次世代車の普及の促進は、その一環といえるでしょう。
一方、地方自治体でも、ゼロカーボンシティ宣言やEV導入補助など、独自の施策が打ち出されています。建築物の省エネルギー基準の引き上げなど、生活インフラ全体に対する環境配慮も強まっており、地域レベルでの対策が進んでいる状況です。
ご家庭でできる排気ガス削減の取り組み
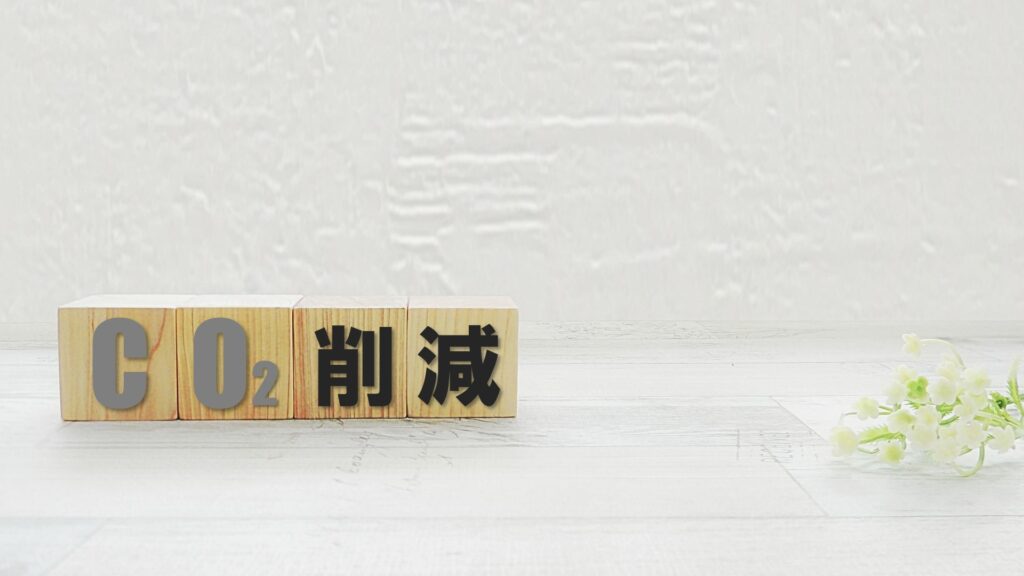
排気ガス問題の解決は、国や企業だけの責任ではありません。私たち一人一人の日常生活における選択や行動の積み重ねが、大きな削減効果を生み出します。日常生活から始められる排気ガス対策を確認しておきましょう。
車の使い方を見直して排気ガスを減らす
日常生活の中で排気ガスの多くを占めるのが、自動車の利用です。買い物や通勤など、少しの工夫で車の使用頻度を減らせば、排気ガスの削減に貢献できます。
例えば、近距離の移動には自転車や徒歩、公共交通機関の利用を優先することで、ガソリンの燃焼量を減らすとよいでしょう。
また、アイドリングストップや急加速を控えるなど、エコドライブの実践も効果的です。電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)など、環境負荷の少ない車種へ買い替えるのもおすすめです。
省エネ家電と節電行動で消費エネルギーを抑える
ご家庭内の電力消費量を減らすのも、排気ガスの発生量の削減につながります。エアコンや冷蔵庫などの電化製品を、省エネ性能の高い製品に買い替えたり、照明をLEDに交換したりすることで、年間の消費電力量の大幅な削減が可能です。
また、使用していない電気製品は主電源を切り、待機電力を減らすなど、小さな節電の積み重ねも有効です。無理のない範囲で省エネの工夫を取り入れることが、環境と経済の両面にとって良い選択といえます。
電力の選び方で間接的な排出を減らす
電力の供給元を見直すのも、排気ガスの削減に寄与する有効な方法です。再生可能エネルギーを中心に供給する新電力へ切り替えることで、電力を使うことで生じる排気ガスの排出量を、間接的に抑えられます。
近年は「グリーン電力」や「再エネ100%」など、環境に配慮した電力プランが増えているため、この機会に電力会社の乗り換えも検討してみてはいかがでしょうか。
環境に配慮するなら新電力への乗り換えも検討

排気ガスの削減に向けた取り組みは、個人から国レベルまで、さまざまな段階で実施すべき重要な課題です。ご家庭でも、自動車の使い方の見直しや省エネ家電の導入、節電の工夫など、日常生活の中でできる取り組みは多岐にわたります。
特に、再生可能エネルギーの比率が高い新電力への乗り換えを検討することで、電力使用に伴う排気ガスの排出量を効率的に削減できます。この機会にご家庭のエネルギーの使い方を見直し、環境にやさしい選択を取り入れてみましょう。
なお、数ある新電力の中でも、エンワンでんきは二酸化炭素の排出量実質ゼロで、環境価値の高い「カーボンニュートラルでんき」を提供しています。ご家庭に合った料金プランを選びやすく、手続きも簡単なので、この機会にぜひ利用をご検討ください。
-

エネワンでんき編集部
-
エネワンでんき編集部は、電気代の見直しや節約の工夫、電力会社の選び方など、暮らしに役立つエネルギー情報をわかりやすく丁寧に発信し、日々の生活に寄り添う情報をお届けします。
 【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル
【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル





