
酸性雨の原因や影響とは?日本での取り組みや家庭で簡単にできる対策をご紹介
酸性雨の原因や影響とは?日本での取り組みや家庭で簡単にできる対策をご紹介
天気予報で「酸性雨が降る」と聞いて、「人体に影響があるのでは」と不安を感じたことはありませんか。酸性雨は人体だけでなく、河川や森林、建造物などにもさまざまな悪影響をおよぼします。今回は、酸性雨はなぜ発生するのか、通常の雨との違いは何かを解説したうえで、日本における酸性雨の現状や、酸性雨を減らすためにできる取り組みをご紹介します。
【目次】
酸性雨ってなに?

まず、そもそも酸性雨とは何か、通常の雨とは何が異なるのかを解説します。
酸性雨とは
酸性雨とは、二酸化硫黄や窒素酸化物といった酸性物質が溶けた雨・雪・霧のことです。
酸性雨が降った河川や土壌は酸性になり、そこに生息する生き物の生態系に悪影響をおよぼします。また、酸性雨が金属を錆びさせ、コンクリートを溶かし、建造物や文化財が劣化してしまうこともあります。
酸性雨と通常の雨との違い
酸性雨と通常の雨を区別する指標の一つが、pH(ピーエッチ/ペーハー)と呼ばれる値です。pHは「液体がアルカリ性か酸性か」を示す指標で、一般的に低くなるほど酸性、高くなるほどアルカリ性となります。
酸性とアルカリ性の中間である中性のpHは7です。自然の雨のpHの目安は5.6程度とされているため通常の雨でも酸性ではありますが、酸性雨はそのpHの酸性度がより高くなっている雨を指します。
酸性雨の原因

酸性雨の発生原因には、自然に起因するものと人為的なものがあります。それぞれについて説明します。
酸性雨の自然的要因
先ほども述べたように、酸性雨は、雨・雪・霧に二酸化硫黄などが溶け込むことによって発生します。
二酸化硫黄は、火山活動などの自然現象によって放出されることがあります。放出された二酸化硫黄が大気中で酸化され、硫酸の微粒子となり、雨などに溶け込んで酸性雨を発生させるのです。
酸性雨の人為的要因
自然だけでなく、人間の営みも酸性雨を引き起こす要因となります。
18世紀の産業革命から、世界で急速に工業化が進みました。工業化は暮らしを便利にする一方で、大気中に多くの汚染物質を放出する原因にもなりました。
工場から排出される排気ガスには、二酸化硫黄や窒素酸化物が含まれています。また、20世紀以降に広く普及した自動車も、エンジンを動かす際に同じく二酸化硫黄や窒素酸化物を排出します。これらが大気中で酸化し、酸性雨のもととなるのです。
酸性雨の影響

酸性雨が降ると、人体や自然、建造物などにさまざまな悪影響をおよぼします。以下では、どのような悪影響があるのかをご紹介します。
人体への影響
酸性雨は、人体に健康被害をおよぼすおそれがあります。1974年7月、関東地方で降った酸性雨により、3万人を超える人々が目や皮膚の刺激を訴える被害がありました。
なお、酸性雨は雨よりも霧の状態になることで原因物質を吸い込みやすくなり、呼吸器などに深刻な健康被害をもたらすおそれがあるとされています。1952年にイギリスで起こったロンドン殺人スモッグ事件では、pHが1.5といわれる強い酸性の霧が発生したことにより、5日間で4,000人もの人が亡くなりました。
河川・湖沼への影響
酸性雨が流れ込んで河川や湖沼、池などが酸性化すると、これまで暮らしていた魚などの水生生物が住めなくなってしまいます。特に雪の降る地域では、春になると酸性雨の雪が溶けて河川や湖沼に流れ込み、一気に酸性化が高まるケースもあります。
このように、酸性物質を取り込んだ積雪が溶け出し、河川や湖沼のpHの値が急激に低下する現象を「アシッド・ショック」といいます。
アシッド・ショックを受けた河川や湖沼の生き物は死滅してしまい、産卵のために遡上することもなくなるため、生態系に大きな影響をおよぼしかねません。
1950年代、スウェーデンをはじめとした北欧諸国では、湖沼の酸性化によって多くの魚類が死滅するなどの被害がありました。
地下水への影響
地下水は工業や農業に使われるほか、飲食品の製造や調理、飲料などにも利用されます。そのため、地下水に酸性雨由来の有害物質が流れ込むと、普段わたしたちが飲んでいる飲料水や料理に使う水が汚染されてしまいます。
汚染された水を飲んだり、その水で作った料理を食べたりすることで、さまざまな病気を引き起こすおそれがあるでしょう。
森林への影響
酸性雨が降り注いだことによって、森林が枯死してしまう被害もあります。特に針葉樹林は、何年も落葉せず同じ葉をつけているため、酸性雨による影響が大きいといわれています。
一見問題なく生えているように見える木が、実は酸性雨によって抵抗力が弱まっており、寒波や台風などの刺激を受けて突然枯れ始め、大きく崩壊するケースもありました。
また、酸性雨が土壌に染み込み、土質を酸性に変えると、植物が成長するために必要な栄養分が流れ出てしまいます。そのため、木々が育たない土壌になってしまうのです。
建造物への影響
酸には、金属をさびさせる性質や、コンクリートの成分のカルシウムを溶かす性質があります。そのため、pHが低い酸性雨が降ると、建造物が劣化・損傷してしまいます。
酸性雨は、先祖から受け継がれてきた重要な文化財にも悪影響をおよぼしかねません。ギリシャのパルテノン神殿は大理石でできていますが、その貴重な大理石彫刻が酸性雨によって溶けてしまう被害が出ています。
日本にとっての酸性雨
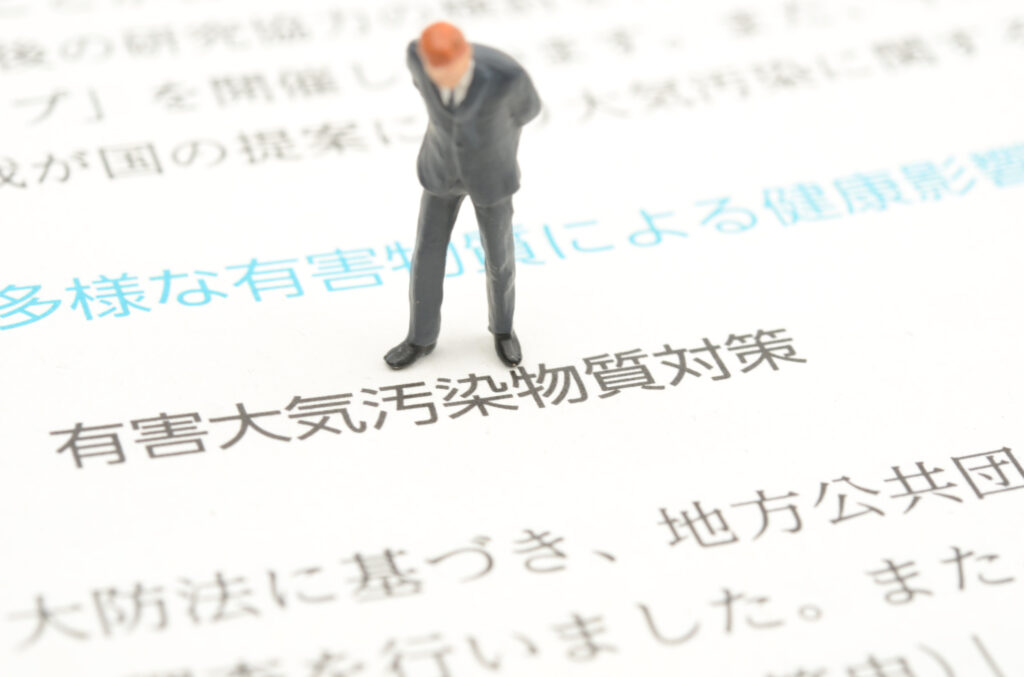
世界中でさまざまな悪影響をおよぼしている酸性雨ですが、日本の現状はどうなっているのでしょうか。日本における酸性雨の現状や取り組みについて説明します。
日本における酸性雨の現状
日本における酸性雨の問題はいまだ解決しておらず、今もpH5.6以下の酸性雨が降っています。ただし、日本国内や国外で酸性雨の原因となる排出ガス削減に向けた政策や規制が進められた結果、1990年代初期と比べると改善の傾向が見られます。
化石燃料への依存度の低下やクリーンエネルギーへの移行、省エネ技術の導入などにより、酸性雨の原因となる有害物質の排出量削減につながりました。
酸性雨に対する日本の取り組み
環境省では「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」を実施しています。全国に測定所を設置し、二酸化硫黄や窒素酸化物といった酸性雨の原因物質をモニタリングする取り組みで、酸性雨の影響の早期把握や将来の予測に役立てています。
この取り組みは、前身の調査を含め1983年(昭和58年)度から現在まで行われているものです。2023年(令和5年)度の酸性雨調査結果での降水中pHの全国平均は4.98で、いまだ酸性雨問題は解決していません。
家庭で簡単にできる酸性雨対策

国が行っている酸性雨対策を紹介しましたが、個人でもできることはあります。ここからは、誰でも簡単にできる酸性雨対策の心がけをご紹介します。
省エネを心がける
酸性雨の原因である硫黄酸化物や窒素酸化物は、発電所で電気を作る際にも排出されます。つまり、電気の使用量を減らすことで、酸性雨の原因物質を減らせるのです。
使わない電気はこまめに消す、LED照明に替えてエネルギー消費量を少なくするなど、できる対策から始めてみましょう。再生可能エネルギーの導入も、化石燃料の使用量を減らすことにつながるため、ぜひ検討してみてください。
自転車や徒歩移動を心がける
自動車から排出される窒素酸化物は、酸性雨の大きな原因の一つです。少しでも原因物質を減らすために、国を挙げて自動車が排出するガス量の規制などが進められてきました。
個人では自動車の利用をなるべく控えて、自転車や徒歩移動を心がけることが大切です。遠出するときは、公共交通機関を利用するのもよいでしょう。
酸性雨は身近なことから簡単に対策できる

酸性雨には有害物質が含まれており、人体や森林、建造物に悪影響をおよぼします。日本における酸性雨の問題は以前よりも改善したものの、いまだ解決はしておらず、今後も国を挙げて対策に取り組む必要があるでしょう。
個人でも、省エネを心がける、自動車を使わず移動するなど、毎日の生活のなかで酸性雨対策に取り組むことが大切です。
エネワンでんきの「カーボンニュートラルでんき」なら、二酸化炭素を排出しないという環境価値が付与された電気を利用できます。申し込むだけで環境に配慮できるお得なプランのため、毎日使用する電気で環境問題対策をすることができます。
-

エネワンでんき編集部
-
エネワンでんき編集部は、電気代の見直しや節約の工夫、電力会社の選び方など、暮らしに役立つエネルギー情報をわかりやすく丁寧に発信し、日々の生活に寄り添う情報をお届けします。
 【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル
【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル





