
同棲の生活費はどのくらい?管理方法の決め方や節約のコツもご紹介
同棲の生活費はどのくらい?管理方法の決め方や節約のコツもご紹介
同棲生活では、一人暮らしに比べて生活費を抑えやすい一方で、2人でお金の管理をする必要があります。毎月どれくらいの費用がかかるのかを把握し、ストレスのない同棲生活を楽しみましょう。生活費の管理方法や節約のコツも解説します。
目次
同棲の生活費の平均はどのくらい?

同棲生活の家計を考える場合、まずは世の中の2人世帯の生活費がどのくらいなのかを把握することが大切です。2024年における2人世帯の1カ月の生活費を見てみましょう。
同棲の生活費の内訳
総務省統計局が公表する「家計調査 家計収支編」によると、2024年における2人世帯の生活費の内訳は次の通りです。
| 食費 | 75,374円 |
| 住居 | 19,385円 |
| 光熱・水道 | 21,120円 |
| 家具・家事用品 | 11,885円 |
| 被服および履物 | 7,366円 |
| 保健医療 | 15,893円 |
| 交通・通信 | 35,314円 |
| 教育 | 571円 |
| 教養娯楽 | 26,776円 |
| その他の消費支出 | 55,070円 |
| 合計 | 268,755円 |
このデータには持ち家の世帯も含まれるため、賃貸住宅の場合[1] [2] 、住居費がこれより高くなる可能性があります。また、その他の消費支出には、小遣い・身の回り品・交際費などが含まれます。
支出のうち最も大きな割合を占めているのが食費です。水道光熱費や交通・通信費も、負担が大きくなりやすい支出だといえます。
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)家計調査 家計収支編 二人以上の世帯
同棲の生活費のシミュレーション
手取り額に対する生活費の内訳がわかれば、実際に同棲生活を始めた後のイメージをつかみやすいでしょう。手取り額20万円・30万円・40万円の3パターンに分けて、同棲の生活費のシミュレーションをご紹介します。
<手取り額20万円の場合>
| 食費 | 50,000円 |
| 住居 | 60,000円 |
| 光熱・水道 | 20,000円 |
| 家具・家事用品 | 10,000円 |
| 被服及び履物 | 10,000円 |
| 保健医療 | 10,000円 |
| 交通・通信 | 20,000円 |
| 教育 | 0円 |
| 教養娯楽 | 10,000円 |
| その他の消費支出 | 10,000円 |
| 合計 | 200,000円 |
<手取り額30万円の場合>
| 食費 | 70,000円 |
| 住居 | 80,000円 |
| 光熱・水道 | 20,000円 |
| 家具・家事用品 | 10,000円 |
| 被服及び履物 | 10,000円 |
| 保健医療 | 20,000円 |
| 交通・通信 | 20,000円 |
| 教育 | 0円 |
| 教養娯楽 | 20,000円 |
| その他の消費支出 | 30,000円 |
| 貯金 | 20,000円 |
| 合計 | 300,000円 |
<手取り額40万円の場合>
| 食費 | 80,000円 |
| 住居 | 120,000円 |
| 光熱・水道 | 20,000円 |
| 家具・家事用品 | 10,000円 |
| 被服及び履物 | 10,000円 |
| 保健医療 | 20,000円 |
| 交通・通信 | 20,000円 |
| 教育 | 0円 |
| 教養娯楽 | 30,000円 |
| その他の消費支出 | 50,000円 |
| 貯金 | 40,000円 |
| 合計 | 400,000円 |
手取り額が増えると、住環境のグレードを上げたり、食費に余裕を持たせたりしやすくなります。都市部は家賃が高くなるため、上記の金額で収まらない場合はほかの支出を抑えて調整しましょう。
同棲の生活費の分担・管理方法
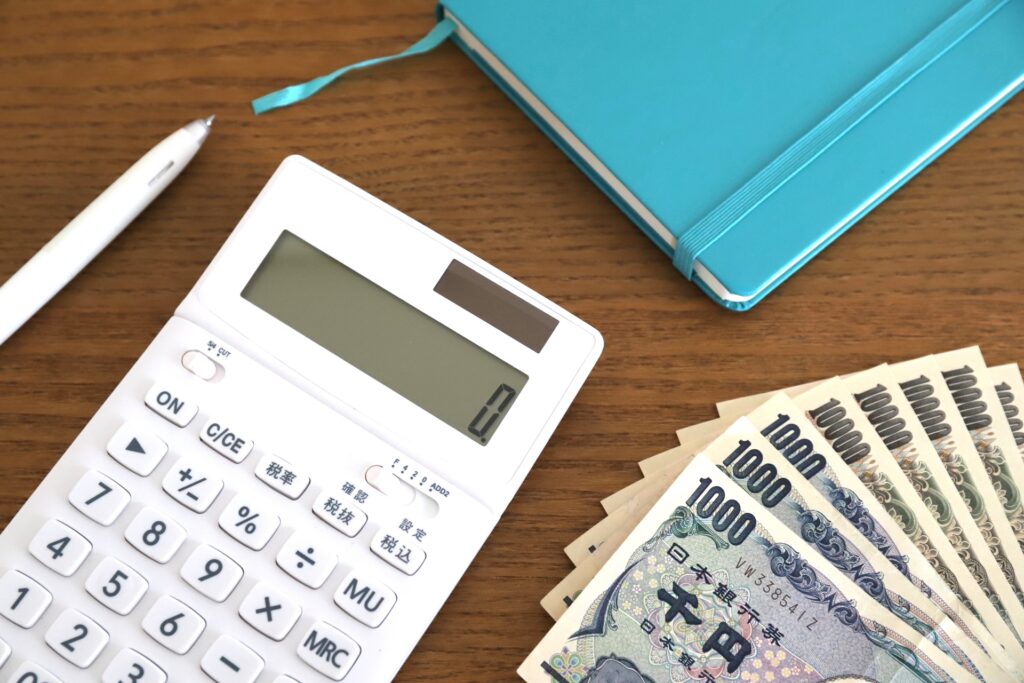
同棲生活では2人の収入をもとに生活費を出し合うため、負担のバランスを考慮しながら管理方法を決めることが重要です。収入や支出の状況によって適した方法が異なるため、以下の3つのパターンを参考に、自分たちに合った管理方法を選びましょう。
決まったお金を共同口座に入れる
それぞれが毎月決められた金額を共同口座に入れることで、家計の管理がシンプルになります。家賃・食費・水道光熱費など、それぞれに関わる支出を共同口座に入れるようにするとよいでしょう。
収入に差がある場合は、2人で負担割合を決めておくことで、お金のトラブルを防ぎやすくなります。赤字にならないよう、決められた金額内に支出を抑えるのがポイントです。
黒字になってお金が余った場合も、貯金に回したり臨時の出費に充てたりできます。金銭的な負担が少ない場合は家事の割合を増やすなど、不満が発生しないように生活全体でバランスを取りましょう。
生活費の総額を2人で折半する
2人の収入が同じくらいの場合は、生活費の総額を2人で折半する方法もあります。例えば、共通の支出を月末に計算して2人で等分するような形です。
この方法ならお互いの負担が平等になるため、万が一同棲生活を解消することになっても、「自分のほうが負担が大きかったのだから返してほしい」といったトラブルを防げます。
生活費を折半する管理方法のデメリットは、お金のやり取りに手間がかかりやすいことです。収支を毎月計算しなければならないため、面倒に感じるケースもあるでしょう。
支出項目ごとにどちらが払うかを決める
同棲の生活費の管理方法としては、支出項目ごとに担当を決める方法も挙げられます。「家賃と水道光熱費は自分、食費とインターネット回線費はパートナー」といった分け方です。2人の収入に差がある場合に適しています。
自分が担当する費用を責任を持ってきちんと支払えば、家計の管理がしやすくなるでしょう。片方の負担が重くなりすぎないよう、バランスを考えて担当を決めることが重要です。
同棲の生活費を抑えるためのコツ

同棲生活で上手にお金を管理しながら、出費を抑えることが重要です。無理なく継続できる節約方法を取り入れ、2人の暮らしを快適に保ちましょう。ここでは、効果的に生活費を抑えるための3つのポイントを紹介します。
家計簿をつける
家計の現状把握ができていない場合、どうしてもぜいたくをしがちになってしまいます。支出の見える化を図るためには、家計簿をつけるのがおすすめです。
家計簿をつけることが習慣化すると、毎月のお金の流れを見ながら削減できるポイントが見つかりやすくなります。2人で家計簿を定期的にチェックし、節約できそうな出費を話し合いましょう。
家計簿アプリを活用すれば、手間を減らしながら家計管理ができるため、継続しやすくなります。銀行口座やクレジットカードと連携できる機能や、カメラでレシートを読み込める機能など、大幅に手間を軽減できる機能が備わっている点が魅力です。
食事は自炊をメインにする
「家計調査 家計収支編」を見ると、食費75,374円のうち、調理食品11,538円・外食10,326円となっています。いずれも食費に対して大きな割合を占めているため、食費の節約を図るなら自炊をメインにすることが重要です。
食費を減らすために意識したいポイントをまとめました。
- 食材をまとめ買いし、買い物の回数を減らす
- できるだけ安い食材を買う
- 職場には弁当や水筒を持っていく
- 外食するならディナーよりランチにする
- コンビニや自動販売機の利用を控える
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)家計調査 家計収支編 二人以上の世帯
固定費を見直す
固定費とは、毎月同じような金額がかかる支出のことです。固定費を節約できれば一定額を継続して減らせるため、大きな収支改善効果を得られます。
主な固定費と節約のポイントは次の通りです。
| 携帯電話代 | 格安SIMや大手キャリアの格安プランに変更する |
| サブスク利用料 | 長期間使っていないサブスクを解約する |
| 保険料 | 無駄なオプションをカットする、ネット保険に切り替える |
| 水道光熱費 | 電力会社やガス会社を見直す |
電気料金が安い電力会社に変更すれば、電気代を削減できる可能性があります。賃貸物件に住んでいる場合も、電力会社と直接契約を結んでいるなら、原則として電力会社の切り替えは可能です。
エネワンでんきは、電力使用量に合わせた最適なプランを選べるほか、さまざまな特典がついたプランも用意しています。電力会社の変更を考えるなら、ぜひエネワンでんきをご検討ください。
エネワンでんきで電気代がいくら安くなるかシミュレーションする
同棲の生活費のよくある疑問
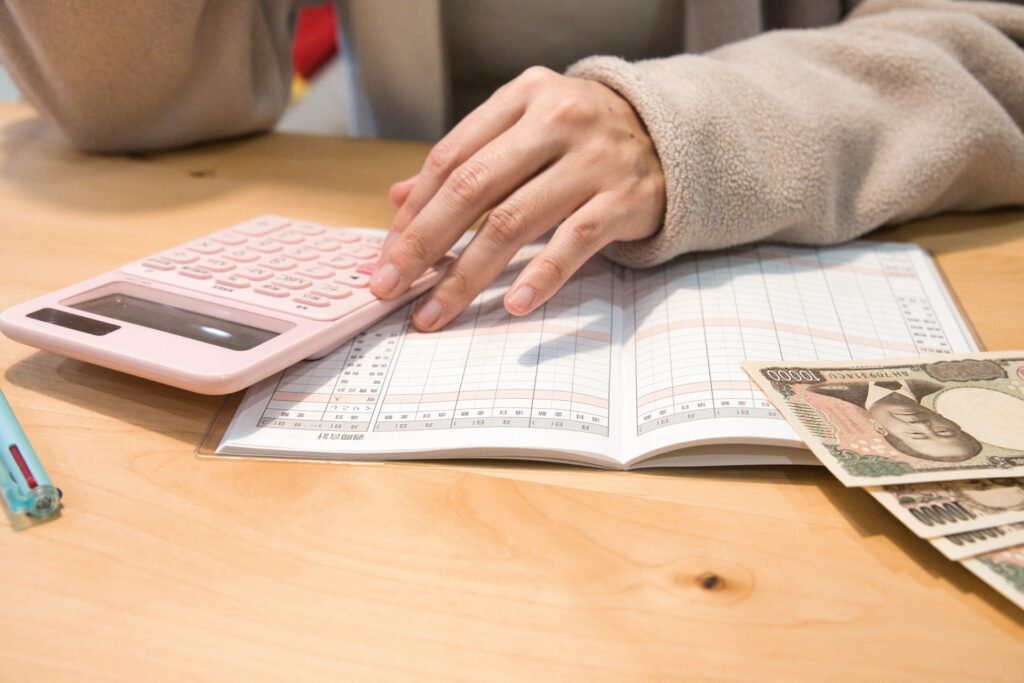
同棲生活を始めるにあたっては、さまざまな疑問が生じがちです。以下に挙げる疑問と回答に目を通し、スムーズに同棲生活を始めるための参考にしましょう。
別々に住むより同棲のほうがお得?
「家計調査 家計収支編」によると、2024年における単身世帯の消費支出の平均は169,547円です。これを2倍にすると、2人世帯の平均268,755円を超えるため、別々に住むより同棲したほうが生活費が安くなるといえます。
また、2人で住居費を出し合うことで、より利便性が高く広い物件に住むことが可能です。職場へのアクセスが良くなるなど、生活の快適性を高めることもできます。
ただし、片方が浪費しがちだったり、お金に対する考え方が大きく違ったりすると、かえってストレスになることもあります。事前にわかることはある程度確かめておくことも重要です。
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)家計調査 家計収支編 単身世帯
同棲より結婚のほうが節約できる?
結婚して法律上の夫婦になる経済的なメリットとしては、扶養に入れることが挙げられます。一定の要件を満たせば、配偶者が「税法上の扶養」や「社会保険上の扶養」に入ることが可能です。
税法上の扶養に入ることで、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられ、節税につながります。また、社会保険上の扶養に入っていれば、配偶者は健康保険料と年金保険料を納める必要がありません。
なお、社会保険上の扶養は事実婚でも可能ですが、税法上の扶養は法律婚のみ対象です。
同棲の生活費で揉めないためのポイントは?
今まで別々の生活を送ってきた2人が同棲を始めると、生活費で揉めるケースがあります。トラブルに発展してしまうのを防ぐためには、お金に関するルールをつくることが大切です。
例えば、「小遣いは月30,000円まで」「プライベートの飲み会の費用は月10,000円まで」といったルールを決めておけば、無駄な出費を抑えやすくなります。ただし、ルールが厳しすぎるとストレスがたまるため、無理のない範囲でルールをつくるのがポイントです。
また、生活費の負担はお互いの収入や支出状況に応じて柔軟に調整しましょう。臨時の出費や将来に備えて、無理のない範囲で貯金もしておきましょう。
同棲の生活費を賢く節約しよう

生活費には、家賃・食費・水道光熱費など複数の項目があり、同棲の際には、2人でルールを決めて管理することが大切です。費用の分担方法を明確にし、家計簿を活用することで、無駄な支出を防ぎながら公平な負担を実現できます。
また、自炊や固定費の見直しなど、日々の工夫によっても生活費を抑えることが可能です。2人で話し合い、無理のない範囲で生活費を見直すことが出来れば、より快適な同棲生活を送ることができるでしょう。
この記事に関連する用語
-

エネワンでんき編集部
-
エネワンでんき編集部は、電気代の見直しや節約の工夫、電力会社の選び方など、暮らしに役立つエネルギー情報をわかりやすく丁寧に発信し、日々の生活に寄り添う情報をお届けします。
 【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル
【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル





