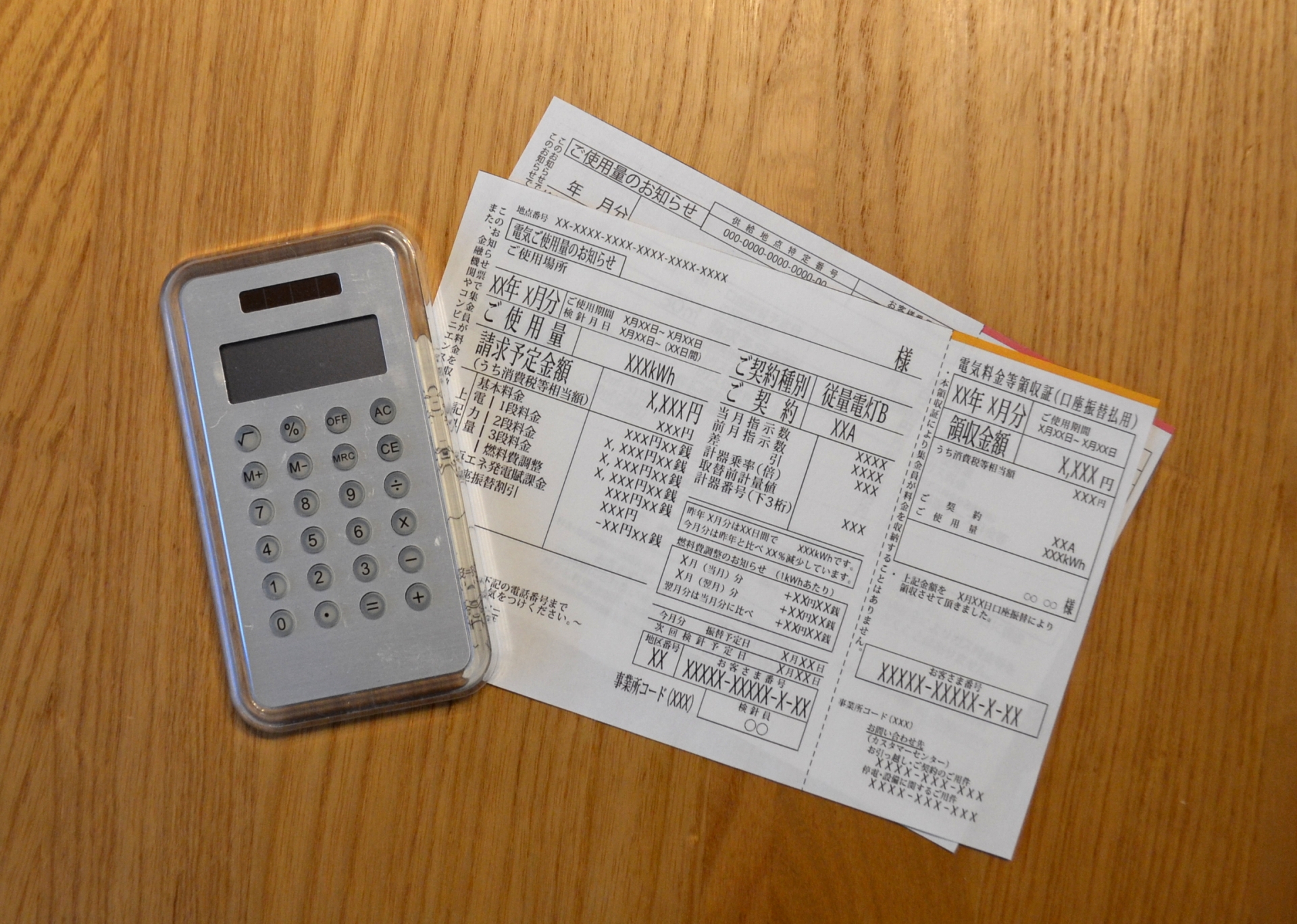生活費の項目の分け方とは?家計管理と節約のコツを紹介
生活費の項目の分け方とは?家計管理と節約のコツを紹介
家計簿をつける際、最初に「生活費の項目」を設定します。項目分けに決まったルールはなく、家族構成やライフスタイルに合わせて自由に決めて構いません。項目分けの一例や家計管理のポイント、固定費の見直し方などを解説します。
目次
生活費とは?基本をおさらい

物価高が進む中、家計管理の見直しのために家計簿をつける家庭が増えています。
家計簿は1カ月の生活費を記録するものですが、「どのような項目を設定すればよいかわからない」という方は少なくありません。まずは、生活費の基本をおさらいしましょう。
生活をする上で必ず必要なお金のこと
私たちは「生活費」という言葉を日常的に使っています。生活費は生計費とも呼ばれ、人々が生活を維持する上で必要なお金です。
総務省統計局では、国民の消費生活の実態を把握するための「家計調査」を行っています。家計調査の中で、生活費は「消費支出」という名称であり、「日常生活で必要な商品・サービスを購入して実際に支払った金額」と定義されています。
以下は、2024年度における1カ月の消費支出の平均額(2人以上の世帯)です。全体の平均は300,243円で、世帯人数別では以下のような結果となりました。
| 世帯人数 | 1カ月あたりの消費支出 |
| 2人 | 268,755円 |
| 3人 | 310,096円 |
| 4人 | 341,400円 |
| 5人 | 359,917円 |
| 6人 | 368,655円 |
※出典:家計調査 家計収支編 二人以上の世帯用途分類 004 用途分類(世帯人員別) | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口
固定費と変動費がある
生活費の項目は、「固定費」と「変動費」のいずれかに分類されます。固定費は、毎月または毎年の支払いがほぼ一定額の支出を指します。「家計の見直しは固定費から」といわれるのは、一度見直すだけで節約効果が長く続くためです。
水道光熱費や通信費は毎月変動しますが、基本料金が決まっているために本記事では固定費と見なします。
変動費は、毎月または毎年の支払いが変動する支出です。毎月必ず発生するものもあれば、冠婚葬祭費や旅行費などのように、突然発生するものもあります。めったに発生しない変動費は「特別費」として管理するのがよいでしょう。
| 代表的な固定費 | 住居費 水道光熱費 通信費 保険料 教育費 自動車費 |
| 代表的な変動費 | 食費 日用品費 交際費 被服・美容費 医療費 娯楽費 |
生活費の項目には何がある?

家計簿をつけるときは、最初に「生活費の項目」を決める必要があります。総務省統計局の家計調査報告を例に挙げながら、代表的な項目と決め方のポイントを解説します。
家計調査報告における項目
家計調査報告とは、約9,000世帯の家計(収入・支出・貯蓄・負債など)を調査した結果をまとめたものです。本調査(家計収支編)では、消費支出(生活費)を10の項目に分けています。
- 食料
- 住居
- 光熱・水道
- 家具・家事用品
- 被服及び履物
- 保健医療
- 交通・通信
- 教育
- 教養・娯楽
- その他の消費支出
「食費」には、菓子類・酒類・飲料・外食費が含まれます。雑費・こづかい(使途不明金)・交際費・仕送り費などは、「その他の消費支出」に該当します。
家計簿の項目を家計調査と統一すると、全国の平均支出と比較しやすくなるというメリットがあります。
家計簿の項目は自由に決めていい
市販の家計簿の中には、生活費の項目があらかじめ記載されているものもありますが、自分たちの家族構成やライフスタイルに合わせて自由に設定して構いません。
月々の支出が少ない項目は、他の項目に合算することで、家計管理が楽になります。逆に、支出が多い項目は「専用項目」を設けるのが理想です。
家計調査において「外食費」は食費に含まれています。外食費が多いご家庭では、「外食費」という項目を作ると、お金の流れがわかりやすくなるでしょう。何でも食費や交際費に入れようとすると、お金の流れが不透明になりやすいので注意が必要です。
項目分けの一例を紹介

使ったお金をすべて記録したい几帳面な方もいれば、大まかな支出の流れが把握できればよいという方もいるでしょう。家計簿は長く続けなければ意味がありません。
自分に合った項目を設定し、半年、1年…と続けることが重要です。参考までに、項目分けの一例を紹介します。
3~4の項目で分類する方法
生活費の項目は、多ければ多いほどよいわけではありません。項目が多すぎると入力の手間がかかり、3日坊主で終わってしまう可能性があります。
家計管理が苦手な人は、「食費」「水道光熱費」「自分にとって必要な変動費の項目(1~2つ)」で分ける方法がおすすめです。
以下のように、支出を「消費」「浪費」「投資」の3つに分けて管理してもよいでしょう。家計を見直すときは、浪費の項目から着手します。
- 消費:生活を維持するために必要な支出(住居費・食費・日用品費など)
- 浪費:衝動買いや無駄遣いに該当する支出(娯楽費や飲み会代など)
- 投資:将来のため使う支出(教育費・セミナー代・保険料など)
8つの項目で分類する方法
生活費をしっかり整理したい人は、項目を8つの項目に分ける手があります。以下は分け方の一例です。固定費と変動費を4つずつピックアップしましょう。
<固定費>
- 住居費
- 水道光熱費
- 保険料
- 教育費
<変動費>
- 食費
- 日用品費
- 交際費
- 医療費
子どもがいるご家庭は「教育費」、美容系の支出が多い場合は「美容代」など、何を項目にするかは、ご家庭によって異なります。
項目が多くなりすぎる場合は、「娯楽費」や「特別費」を設けて、複数の項目をまとめるのがポイントです。特別費には、毎月発生しない特別な支出で、かつ金額が比較的高額なものを入れましょう。
項目分けと家計管理のポイント
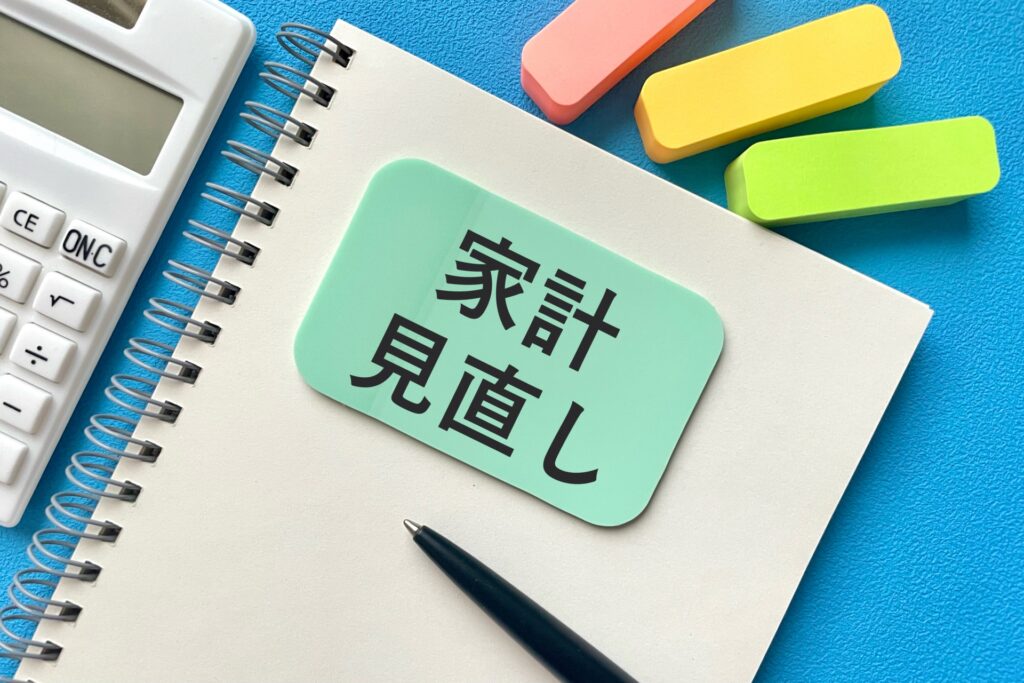
家計管理がスムーズにできるかどうかは、生活費の項目分けに左右されます。初心者が陥りやすい落とし穴と意識したいポイントを解説します。
初心者は項目を一気に増やさない
生活費の項目を分けたものの、「なんとなく管理しにくい」「どこに入れたらよいか分からない支出が出てきた」というケースは多いものです。
生活費の項目は自由にカスタマイズできます。自分たちの消費支出に合わせて変更・調整を加えましょう。
ただし、初心者は項目を一気に増やさないことが重要です。細分化しすぎると、記録に時間がかかって挫折しやすくなります。3~4項目から始め、徐々に増やしていくのが賢明です。
月の途中で変更すると計算が合わなくなるため、新たな項目での記録は翌月から始めるようにしましょう。
家計管理は自分に合ったツールを使う
家計管理の代表的なツールといえば、「家計簿」です。手書きの家計簿がオーソドックスですが、Excelやアプリを利用する手もあります。記録を習慣化するためにも、自分に合ったツールを選択しましょう。
手書きの家計簿は、ちょっとした出来事やアイデアを書き込めるのがメリットです。振り返りがしやすく、自分のスタイルが維持できます。集計の手間を省きたい方は、Excelで管理する方法がおすすめです。
外出先でサクッと記録したい方は、家計簿アプリを活用しましょう。項目の設定・追加・削除が容易にできる上、グラフによる可視化も可能です。レシートを読み込むだけで、自動的に項目分けをしてくれるアプリもあります。
記録するだけで満足しない
家計簿の本来の目的は、お金の流れを可視化し、家計の無駄をなくすことです。家計簿をつけるだけで満足せず、振り返りと家計の見直しを行いましょう。
- 家計簿をつける
- 1カ月の集計を行う
- お金の流れを把握する
- 無駄な支出がないかをチェックする
- 具体的な改善策を考える
無駄を把握した後は、翌月の予算を立てます。例えば、給与が入った時点で、あらかじめ貯金額を差し引き、残りの金額を生活費とする「先取り貯金」は、多くの人が実行している方法です。
給料を項目別に分けて、予算内でやりくりする「袋分け予算」もおすすめです。
真っ先に見直そう!節約効果が高い項目3選

生活費の節約は、固定費からテコ入れするのが基本です。「項目が多くて何から着手すればわからない」という方のために、節約効果が高い代表的な項目を取り上げます。ライフスタイルが変わるときは、必ず見直すようにしましょう。
住居費
生活費の中で、とりわけ大きな割合を占めるのが「住居費」です。一度見直すだけで、毎月数千円から数万円の節約が可能です。
賃貸住宅の場合は、更新のタイミングで家賃交渉をしたり、今よりも賃料が安いところに引越す手があります。単身であれば、ルームシェアや同棲も視野に入れましょう。
持ち家の場合は、住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済で家計負担を抑えます。借り換えをする際は、金利だけでなく事務手数料などの諸費用もチェックしなければなりません。わずかな金利差での借り換えは、逆に負担が増える恐れがあります。
電気代
光熱費の中でも、電気代は家計への負担が大きい項目です。日々の節約はもちろん大事ですが、電力会社や料金プランの見直しを検討しましょう。
電力小売全面自由化の後は、「新電力」と呼ばれる新規の小売電気事業者が市場に参入し、価格競争が起きています。
新電力の多くは、独自のプランやサービスを展開しており、ライフスタイルとの相性が良ければ、電気代を今よりも安くできる可能性があります。
「エネワンでんき」では、月々の電力使用量に応じた3つのプランを用意しています。プランに応じた割引が受けられるほか、環境・社会に貢献できるオプションの追加も可能です。
保険料
保険は「生活を守るための備え」ではありますが、保険料の支払いで家計が苦しくなっては本末転倒。必要な補償や補償額は、世帯主の年齢や家族構成、子どもの数などによって変わるため、定期的に見直す必要があります。
特に、複数の保険に加入している方は、補償内容が重複していないかをチェックしましょう。重複する補償の保険金額が積み上がらない場合、支払った保険料が無駄になってしまいます。
生命保険の場合、健康保険の制度や会社の福利厚生制度が活用できる点を考えると、人によっては保険自体が不要になるかもしれません。ただし、一度解約した後は元の状態に戻せないため、解約は慎重に行いましょう。
生活費の項目はライフスタイルに合わせて

生活費の項目は、固定費と変動費に大別されます。さまざまな項目がありますが、家計簿をつけるときは、自分たちのライフスタイルに必要なものを選択しましょう。
お金の流れが見える化でき、かつ家計の改善につなげられるかどうかがポイントです。
家計簿は記録するだけで終わりではありません。1カ月ごとに振り返りをし、当月の反省点を翌月に生かします。「なぜ節約が必要なのか」「どのくらい貯金をする必要があるのか」など、パートナーと話し合う機会を設けましょう。
この記事に関連する用語
-

エネワンでんき編集部
-
エネワンでんき編集部は、電気代の見直しや節約の工夫、電力会社の選び方など、暮らしに役立つエネルギー情報をわかりやすく丁寧に発信し、日々の生活に寄り添う情報をお届けします。
 【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル
【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル